
2015.07.09

2011年3月11日。当時生まれた赤ちゃんは、今は中学生。仮設住宅で幼少期を過ごした子どもたちは高校生へと成長しています。被災経験はあるけれど、震災の記憶がほとんどない中高生たち。しかし、震災がもたらした生活環境や家族の変化などが、今も彼らに何らかの影響を及ぼしています。
子どもたちに今も寄り添い活動を続けるハタチ基金の支援団体の多くは、被災した地域の外からやってきた若者たちが立ち上げた団体です。震災から間もなく14年が経つ中、この地に魅了され移住し、活動に参加する20代もいます。
その一人、「一般財団法人まちと人と」で働く野内杏花里さんに、今、東北の子どもたちにとって必要なことについて伺いました。

一般財団法人 まちと人と 野内 杏花里(のうち あかり)さん
東京都出身。山形にある東北芸術工科大学 コミュニティデザイン学科に入学し、子どもの居場所づくりについて研究。宮城県石巻市の子ども支援団体で、ボランティアとして居場所づくりを体験しながら、子どもが自分の道を自分で選択できる力を育むために必要なものは何なのかを模索する。大学卒業後は、石巻で活動をする「一般財団法人まちと人と」に入職。中高生の探究活動を支援したり、学校外での体験や出会いの機会をつくっている。
野内さんが子ども支援の道を選ぶまでの思いを綴った記事【東京で生まれ育った私が選んだ道 東北被災地 子どもたちの居場所づくり】もぜひご覧ください。
震災の記憶がない子どもたちに及ぶ “被災の影響”
ーー野内さんは東日本大震災発生時は小学4年生。東京に住んでいたそうですが、2011年3月11日はどのような経験をしましたか?
野内さん:被害の大きさは東北とは比べものになりませんが、東京もけっこう揺れて。あの日は集団下校ではなく一人で帰っていました。親は二人とも自宅から離れた都市部で働いていたので、3日間帰ってきませんでした。両親が帰宅するまでの間、近くの友だちの家で寝泊りをしていました。
ーー小学生だった野内さんは、不安だったでしょうね。
野内さん:子どもながらにただ事ではないと思ったのをよく覚えています。テレビをつけたら津波の映像が流れてきてびっくりしました。その後街中では、原発反対のデモが盛んに行われたりして、自分の周りが突然大きく変化したように感じていました。
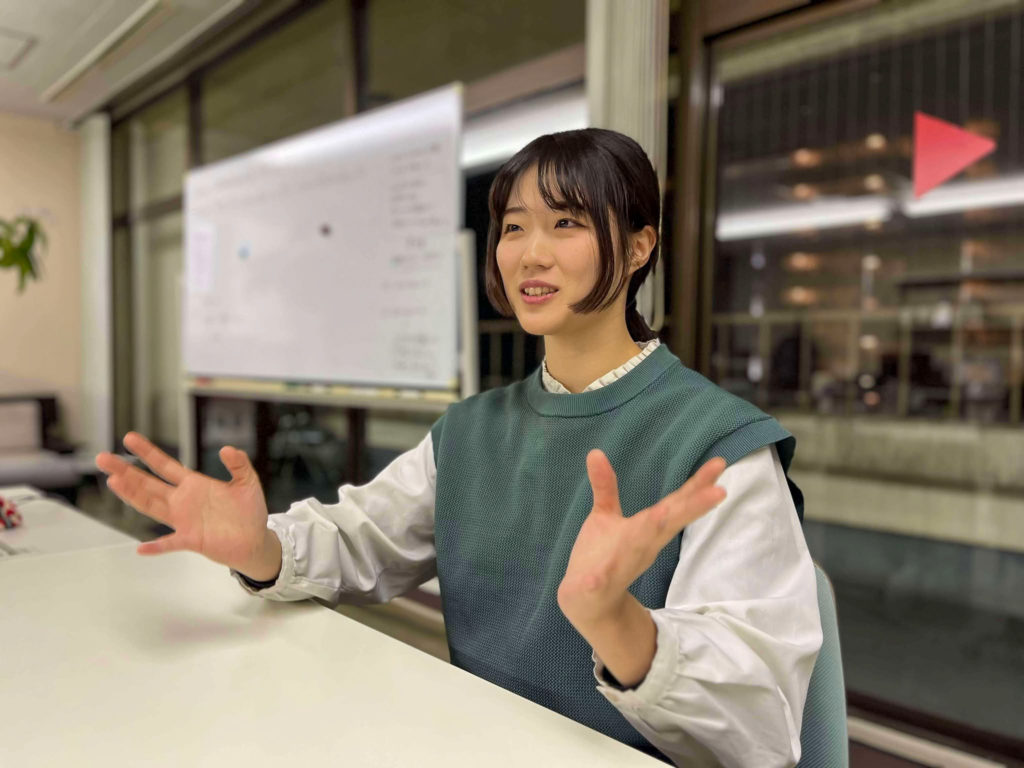
ーー今関わっている高校生たちは、野内さんよりももっと小さかったので、震災のことはほとんど覚えていないですよね。一方で、高校生の親たちは、震災当時は幼子を抱える働き盛りの世代だったわけで、大変な思いをして今日までやってきたと思います。
野内さん:本当に大変だったと思います。普段は子どもと震災の話をすることはあまりないのですが、たまに耳にする話は各家庭さまざまです。ちゃんと震災のことを“教え”として親御さんから聞いている子がいる一方で、家族の中で自分だけが知らない(覚えていない)体験で、居心地が悪いという話も。
ーー居心地が悪い。
野内さん:祖父母や両親、兄姉はつらい経験として刻まれているけれど、自分は覚えていないので、“当事者”ではなく家族の中で自分だけが違うような感覚を持っていると話す子がいて。私のような、“被災地にいるけれど外から来た人”に近い感覚になるのかもしれません。
ーー感覚が似ている野内さんのような存在が身近にいることは、その子にとって良いこともあるのではないでしょうか。
野内さん:実際、大学時代にボランティアで子どもたちの居場所づくりに参加していたとき、私に家族には言えない震災への思いを話してくれた子もいました。少しでも気が楽になってくれたらいいですね。家族内でも被災経験は様々で、覚えていない子にとっては、家族とは話せない話題になっているのかもしれません。


野内さん:今、高校生と関わっていて思うのは、親世代があまり地元に良いイメージを持っていないことが子どもたちにも影響している気がしていて。もしかしたら震災以前からかもしれませんが、自信を持って、「地元で就職してここで暮らすことが楽しい人生になる」と言える世代が少ないように感じています。そのため、子どもたちも地域に関心を持てないんですよね。
地元を出て東京など都市部に行くことは悪いことではありませんが、石巻を出る理由がマイナスの理由ではなくて、ふるさとに誇りを持てた上で出る選択をしたほうが、その後の人生にとっても良い影響を与えてくれると思います。
ーーそのために今、野内さんは活動をしているんですね。
野内さん:地元石巻が好きで、自分の居場所が石巻にある。そう思ってから全国どこへでも好きなところへ羽ばたいて行って欲しいですね。そのために今、できる限りたくさんの地域の大人たちと関わる機会を高校生につくっています。
“自分軸”で動ける力を育む ボランティアプログラム「まきボラ」
ーー具体的には、今どんな支援を行っているんですか?
野内さん:一つは、石巻市内の高校で探究の授業のサポートを行っています。個々が興味を持ったテーマで探究を進めていけるように学校の先生と連携して考えたり、高校生が主体的に動けるようにサポートをしています。
探究活動は、自分が暮らす地域やそこで暮らす大人たちを知るきっかけとなり、自分の自信や誇りにも繋がるので、高校生にとって貴重な機会だと考えています。

ーーサポートをする中で難しさを感じることはありますか?
野内さん:自分事として取り組めない生徒はどうしてもいますね。やらされている感があって。探究の授業はとことん楽しんでやってもいいのですが、そういったことをあまり伝えられていないという課題も感じています。
内容は何でも良いので、自分で納得感を持って探究活動をすることが大事で。自分がやってみたいと思ったことに取り組んだり、大事だなと思いながら活動をする子がいる一方で、進路や成績への影響、他人からの評価を気にしながらやっている子もいます。“自分軸”ではなく“他人軸”で動いている。
ーー他人軸。
野内:自分の意思や考えを軸に探究活動をしていない高校生は、どんなに活動を進めても、最後は「誰かに言われたから」「自分が本当にやりたかったことではない」となってしまうので、そういった生徒のサポートは難しいですね。
自分軸で動けている子は、何も言わなくてもどんどん勝手に自分で前に進んでいきます。人に評価されるためなど、他人軸で動いてる生徒は、どれだけサポートをしても、行き着く先が自分ではなく他人なので。誰のために活動しているんだろうと、そばで見ていてヤキモキするような場面はあります。

野内さん:一般財団法人まちと人とでは、学校や探究の授業以外でも地域や大人たちと関わる場を提供していて。その一つ、高校生と地域をつなぐボランティアプログラム「まきボラ」も担当しています。
ーーまきボラ。なんだか面白そうですね。
野内さん:石巻地域(石巻市・東松島市・女川町)の高校生を対象に、地元の企業やNPOにボランティアとして参加するプログラムです。



ーー自分で申し込むので最初から“自分軸”でスタートできますね。
野内さん:そうなんです。まきボラの良いところは、ボランティアという立場で募っているところにもありますね。普段高校生と探究授業や地域の活動で関わっていると、「何かしたい」と思っても自分から行動することに壁を感じている子が多く、地域活動への参加のハードルが高いのだなと感じます。
ボランティアという形で募ると、“参加する理由”ができるので。自分が相手の役に立つかもと思えたり、将来の進路にもメリットがあるかもと思えたり。インターンにも似ていますが、一度外に出て体験してみるという気軽さは、インターンよりも敷居が低いと思います。1回のボランティアで50人くらい、年間だと100人ほどが登録をしてくれて、実際に活動をする子も多いです。
ーーとっかかりは何でもいいので、まずは外の世界に出て視野を広げるということですね。
野内さん:外に出て才能が開花する子もいますよ。例えば、IT関係の方々と関わる機会を通して、実は自分がITに興味があったことに気づいた高校生も。ボランティアを通して、自分の好きなものを発見できたと話していました。
ーー自分の興味に気づけるのは大きいですね。
野内さん:失敗したり、成し遂げられなかったとしても、自分が納得感を持ってできたという経験があると、その後の人生において支えになると思っていて。
そのためには、今自分がいる小さな世界の外に出てチャレンジをしたり、新しい出会いを経験する、つまり“越境する”ことは必要不可欠だと思うんです。
ーー越境とは具体的にはどういうことなんでしょうか?
野内さん:自分が知らない世界に飛び込んで、新しい人との出会いや繋がりを通じた経験を重ねることだと、私は考えています。
海外留学や知らない土地で暮らしてみるのもいいかもしれませんが、ハードルが高いので、まずは身近なところから。地域の大人たちとの交流を通して、“人の越境”を経験する機会をつくっていきたいです。
取材・文 石垣藍子
東日本大震災で被災した地域では、今もなお、多くの支援団体が継続して子どもたちを支えています。震災直後から子ども支援を続けている人たちの思いが、野内さんのような20代30代の若者にバトンが渡り続いていく。彼らの存在は、震災の記憶がない世代にとって拠り所となり、地域の大人たちと次世代をつなぐ架け橋となっています。

※伴走者合宿について詳しくはこちらの記事【東北被災地で始まった子どもの伴走支援 60人が本気で考えた 今の時代に必要な教育とは】をご覧ください。
被災地で14年間積み上げられてきた経験は、東北のみならず、2024年に起きた能登半島地震の被災地でも役立てられています。また、教育の多様性が求められる昨今、子どもたちの伴走支援は、被災した地域に限らず、日本全国で必要不可欠なものになっています。東北で築かれた“新しい教育の形”が日本の子どもたちの支えとなるように。ハタチ基金は今後も活動を続けて参りますので、応援のほどよろしくお願いします!

2013.12.24